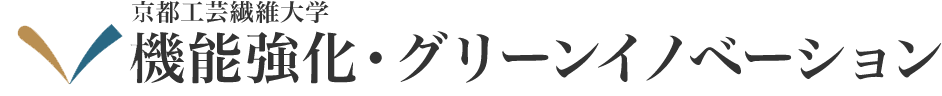日本、欧州、北米のパワーエレクトロニクス関連コンソーシアムが国際連携
パワーエレクトロニクスをめぐる世界情勢
パワーエレクトロニクスは、電力網などのより基幹的な部分に応用の幅を広げつつあるなか、個別の企業や研究機関の取り組みだけでは対応出来ず、業界全体として規格の統一やロードマップの策定など、コンソーシアムとしての活動が必要となってきます。
ドイツを中心とするEUではECPE (European Center for Power Electronics)、北米ではCPES (Center for Power Electronics System)、また日本でも近年設立されたNPERC-J (New Generation Power Electronics and System Research Consortium of Japan)が中心となって業界を取りまとめています。
この三者間でもMOUが結ばれており、共同研究開発や情報公開が活発に行われています。門教授は、NPERC-Jの執行部の一人として参画し、そのMOUの枠組みの中で、京都工芸繊維大学としてEUとの共同研究を行っています。

写真1 NPERC-JとECPEとの国際連携協定調印
大橋・特任教授(NPERC-J理事長)とDr. L. Lorenz(ECPE President)

写真2 NPERC-JとCPESとの国際連携協定調印
大橋・特任教授(NPERC-J理事長)と
D. Boroyevich(バージニア工科大学教授、CPES Co-director)

写真3 三組織代表の集合写真
大橋・特任教授(NPERC-J理事長)、本学の門教授(NPERC-J理事)、二宮・特任教授(NPERC-J監事)、Dr. L. Lorenz(ECPE President)、 D. Boroyevich(バージニア工科大学教授、CPES Co-director)
システム層ユニット招致への布石
2015年5月27日に、日本のNPERC-J、欧州のECPE、北米のCPESが一堂に会し、国際連携協定に調印をしました。本学からも、NPERC-Jの理事を務める門教授が参加しました。
パワーエレクトロニクスの実証データ蓄積のための環境整備
Y字型 電力ルーターの開発
本ユニットではパワーエレクトロニクスの中でもより上層のネットワーク部分を担当しています。太陽光発電や風力などの自然エネルギー、蓄電池、既存電力網などを効率良く変換連結し、需給状況の変化に応じて安定的に電力供給、家庭間などローカルな範囲で電力の融通・効率化を図るマイクログリッドの概念が重要になってきます。そのためには、パワーデバイス単体だけでなく、システム化、さらにはネットワーク化して、実証データを得ることが重要となります。
これを実証するために3ポートのY字型電力ルーターの開発を行っています。
本機器はDC/DC、AC/DC変換ユニットと制御ユニットからなります。通常のコンバータと比較して、外部に接続可能な端子が3つ存在していることが挙げられます。3端子になることで、図3にあげるようにY字型ルーターは、家庭内だけではなくて家庭やオフィスなどで網目状にネットワークをはりめぐらさせることができます。Y字型電力ルーターはマイクログリッドを身近なものにするためのキーデバイスになることが期待されています。

図1 Y字型電力ルーター 1号機
研究室の学生が中心になって設計作製した初号機。この当時はまだY字型の外見ではなかった。

図2 Y字型電力ルーター 2号機、3号機
企業の協力も得ながら実装を行い、コンパクトに仕上げた試作機。視覚的にも3端子=Y字型であることが分かるようになった。直流400Vで10kWの電力の流れを制御できる。
研究拠点の確立に向けて実証デバイスをもとに共同研究、ユニット招致に向ける
世界的にもマイクログリッドなどの研究開発は活発に進められていますが、網目状の電力ネットワークの構築に適しており、最初から民生用への展開を意識した制御機能をもつY字電力ルーターを用いての実証試験は、ほとんど例がありません。そのため、Y字電力ルーターを用いた電力ネットワークの小規模テストベッドを本学内に構築して、実証データの収集手段、場を提供できるというメリットを前面に押し出し、コンソーシアムのネットワークも生かしつつ、海外の研究チームと共同研究、引いてはユニット招致に向けて進めていきます。現在、同様の検討を進めているドイツの有力大学から誘致を検討中です。
本研究開発は、NEDOの「次世代パワーエレクトロニクス応用システム開発の先導研究」、文部科学省の「地域イノベーション戦略支援プログラム」の支援を受けています。
「電力」ルーターって何?
家電も太陽電池も電気自動車も、電力ルーターがあれば箱から出して繋ぐだけ
家庭でインターネットをするためにパソコンをイーサネットケーブルで接続するルーターを思い浮かべてください。この場合、パソコンだけでなく、プリンタやデジタル家電、スマホなどが接続され、その接続方式、接続速度、接続している時間帯もバラバラです。それにもかかわらず、ユーザーは何も意識せずに、ただ接続するだけで、すぐに利用できるようになります。「電力」ルーターもこれと似たコンセプトで、誰でも繋げば電力融通できるシステムの実現を狙っています。
近年、家庭でも太陽電池や蓄電池、電気自動車など、AC/DC、電圧も100Vだけでなく200Vかそれ以上といったものが混在するようになってきました。現時点ではこれらに対応するために、特別な機器を用いて、専門業者が工事を行う必要がありますが、電力ルーターは箱から開けて自分で接続したらすぐに使えることを目指しています。

図3 Y字型電力ルーターの利用イメージ