 |
 |
|
|
 |
| 概 要 |
| 現代社会は,気候変動,感染症,人口減少など,我々の社会はさまざまな危機に晒されています.本ラボでは,電子システム・機械・情報の近領域融合研究を推進し,モビリティ,マニュファクチャリング,インフラ等の分野において,社会の低炭素化と持続可能性維持のためのグリーンなデジタルトランスフォーメーションを牽引します.その牽引の柱として「近領域研究」を立ち上げ,これまで近くて遠かった本学設計工学域の電気電子,機械,情報の融合研究により,学内の活性化を図って参りました. 2025年度より、京都グリーンラボのミッションが大きく変わりました。ラボ長の小林教授がプロジェクトマネージャを務めているムーンショット目標6の研究課題「スケーラブルな高集積量子誤り訂正システムの開発」の研究推進を主なミッションとし、量子コンピュータを制御、エラー訂正する古典エレクトロニクス(集積回路)に関する研究を推進しています。近い領域での学際研究を目指した近領域研究のうち、山川教授を中心としたシミュレーション関係で新たに「高性能シミュレーション研究センター」が設置されました。 |
| ・ | ユーリッヒ研究センター(ドイツ)のDr. Dennis Nielinger が来訪されました。 量子コンピュータのハードウェアシステムの設計とモデリングに取り組んでいるユーリッヒ研究センター@ドイツ のデニス・二―リンガー博士が12月4日に本学・京都グリーンラボの中核、小林研究室 (集積システム講座) に来訪されました。京都グリーンラボのラボ長・小林教授、運営委員・高井教授、新谷准教授が応対し、双方で研究開発を進めているスケーラブルな量子コンピュータ実現のための古典ハードウェアの取組みを紹介、情報交換を行いました。 Dr. Dennis Nielinger は、Universität Duisburg-EssenでPhDを取得し、現在ユーリッヒ研究センターの科学コーディネーターとして活躍されています。
|
|||||||
| ・ | ラボ長の小林和淑教授が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「ムーンショット型研究開発事業」のプロジェクトマネージャーに再選出されました。(10月6日公表) 詳細は、本学ホームページの学内ニュースのプレスリリースをご覧ください。 |
|||||||
| ・ | 京都グリーンラボ、学内公開講演会を開催し、Google Quantum AIのDr. Joseph Bardin(マサチューセッツ大学アマースト校・教授)に講演いただきました。 2025年10月24日(金) 16:10-17:10 開催し、教職員・学生合わせ31名に参加いただきました Joseph Bardin 教授は、Google Quantum AI チームの研究科学者であり、量子コンピューティング向け集積エレクトロニクスの研究に取り組んでおられます。2009年にカリフォルニア工科大学で博士号を取得し、2010年にマサチューセッツ大学アマースト校に着任され、2020年より同校の教授を務められています。現在はGoogle Quantum AIチームの研究者と同校の教授を兼任されています。 Joseph Bardin 教授には、"Building an error-corrected superconducting quantum computer: progress and outstanding challenges" と題し、エラー訂正機能付き超伝導量子コンピュータの構築に関するその進化と現代に置ける未解決の課題について講じていただきました。 |
|||||||
| ・ | 京都グリーンラボ、学内公開講演会「最先端集積回路」を行いました。 電子システム工学課程・専攻の集積システム講座の学生向け及び学内公開講演会として、2025年6月16日(月) にシニアフェローのTSMCの新居氏、キオクシアの田中特任准教授の特別講演会を行いました。講演1ではTSMCの集積回路設計の最新動向を、講演2ではリングオシレータ(リング型発振器)を用いたトランジスタ特性の評価解析方法についてご講演いただきました。 講演1: "最先端ロジック混載SRAMの設計事例紹介と最新技術動向" (Introduction of Embedded SRAM Designs on Advanced CMOS Logic 新居浩二 シニアフェロー(TSMC Japan Design Center㈱ 勤務) 講演2: "リングオシレータ回路を用いたトランジスタしきい値劣化のオンウエハ評価・解析" 田中千加 特任准教授(キオクシア㈱ 勤務) |
|||||||
| ・ | 京都グリーンラボ、公開講演会を開催し、IBMワトソンリサーチセンターのDr. Lynne Gignacに講演いただきました。 Dr. Lynne Gignacは35年以上にわたり、IBMのワトソンリサーチセンターにおいて、電子顕微鏡を駆使した材料研究を通じ、ナノテクノロジーの材料、プロセスを評価し改善することに携わってこられた経験をもとにFIBを用いた透過型電子顕微鏡(TEM)のサンプル準備技術についてご講演いただきました。 令和7年5月21日(水)、16:30~17:30 開催。  塩尻 詢 本学名誉教授が講演者を紹介する様子 |
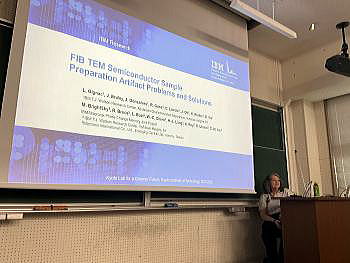 講演の様子 |
||||||
| ・ | サムスン電子の上村大樹様に講師となって頂き、2024年9月6日に特別講演会 「半導体産業ってどんなところ」 を開催しました。 講演者:サムスン電子 上村大樹 博士 (Dr.Taiki Uemura,Samsung Electronics) |
|||||||
| ・ | キオクシアの方々に講師となって頂き、2024年8月5日に「集積回路工学特論]の特別講義を開催しました。 講義の様子 |
|||||||
| ・ | 大学広報誌 KITnews vol.66 (2024.7)に 京都グリーンラボの紹介が掲載されました。 |
|||||||
| 沿 革 |
| 「エネルギーの高効率利用」に関する成果を発展させ,京都地域で推進されている「京都次世代エネルギーシステム創造戦略」に参画し,本学にグリーンイノベーション分野の研究拠点を確立することを目指し,平成27年(2015年)にグリーンイノベーションセンターが発足し,平成30年(2018年)10月の研究力及び産学連携機能強化の一環として重点研究グリーンイノベーションラボに改組されました.グリーンイノベーションラボでは,複数の外部資金をもとに,研究者の集積を図り,パワーエレクトロニクスと高度通信機能を融合した新しい電力制御システムなどを提案し,プロトタイプ製作を進めるなど,本学の機能強化事業のグリーンイノベーション分野の研究開発を進める中心となりました.令和4年に,さらなる研究力強化を目的として,ものづくり教育研究センター(現オープンファシリティセンターものづくりユニット)の研究分野を統合し,「京都グリーンラボ」が発足しました. 平成28年度文部科学省「先端研究基盤共用促進事業・新たな共用システム導入支援プログラム」により,様々な装置をクリーンルームに集結し,共用で使用できる体制を構築してきました.平成28年度文部科学省補正予算「地域科学技術実証拠点整備事業」により本学の強みであるスマートグリッド分野(エネルギー配分を効率化し省エネを目指す研究分野)などの研究成果を事業化につなげるために,国立大学で初めて国際規格に適合した電波暗室等の設備整備を行いました.電波試験技術者国際資格 iNARTE-EMCエンジニアの資格を有する特任専門職のもと,特に新たな革新的なパワーデバイスや装置の開発において,研究開発時からトライ&エラーを繰り返しての共同研究につながる場として地域産業界に対して開放しています.令和4年(2022年)の京都グリーンラボの設置に伴い,クリーンルーム,電波暗室の運営はオープンファシリティーセンターに移管しています. 2025年4月より、「京都グリーンラボ」は概要で記載されている通り、新しい「京都グリーンラボ」として生まれ変わりムーンショット(MS)目標6の研究課題「スケーラブルな高集積量子誤り訂正システムの開発」の研究推進を主なミッションとして、量子コンピュータにフォーカスすることとなりました. 旧グリーンイノベーションラボで運営していた電波暗室とクリーンルームについては下記のリンクをご覧ください。 ・電波暗室のご利用はこちら ・クリーンルーム共用化プロジェクトはこちら ・オープンファシリティセンターものづくりユニットはこちら ・未来デザイン・工学機構はこちら |
| このページのトップへ |
| 構成員 |
| 2025年度~ 新生・「京都グリーンラボ」構成員 |
|
| このページのトップへ |
| 2024年度の京都グリーンラボの報告書はこちらをご覧ください。 2023年度の京都グリーンラボの報告書はこちらをご覧ください。 2022年度の京都グリーンラボの報告書はこちらをご覧ください。 2019年度から2021年度までのグリーンイノベーションラボの報告書はこちらをご覧ください。 2018年度以前のグリーンイノベーションセンターの成果はこちらをご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------------- 京都グリーンラボ2023年度近領域研究成果報告会を開催いたしました。 2023年度近領域研究成果報告会 日時:2024年3月19日(火)14:00~17:00 場所:京都工芸繊維大学 60周年記念館 報告会内容の詳細は、こちらをご覧ください。 講演資料は、こちらからダウンロード可能です。(順次公開中) キックオフシンポジウムを開催致しました。 京都グリーンラボ / ムーンショット目標6 課題:「スケーラブルな高集積量子誤り訂正システムの開発」 日時:2022年11月18日(金) 13:00 場所:京都工芸繊維大学 60周年記念館 開催報告は こちら に公開しております。 (公開可能な講演資料もこちらからダウンロード出来ます。) 概要報告書は こちら |
| 主なプロジェクト |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
| このページのトップへ |
| 〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町1 京都工芸繊維大学 未来デザイン・工学機構 京都グリーンラボ メールアドレス: greenlab[アットマーク]kit.ac.jp |